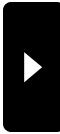2016年05月06日
2016年04月06日
2016年04月02日
タムラソウ
タムラソウ (キク科)
2010年9月10日、長野県戸隠山。
アザミのような花だが、葉や茎には棘がない。アザミ属ではなくタムラソウ属とのこと。
総包片は反らない。淡黄褐色で先が尖る。
葉は羽状に深く裂ける。棘はない。
2016年03月22日
2016年03月18日
2016年03月07日
2016年03月04日
オヤマボクチ
オヤマボクチ (キク科)
2010年9月10日、戸隠山。
これは蕾。アザミのような花が咲くが鮮やかではない。蕾のクモ毛が特徴の一つ。
頭花がうつむく。
葉はフキの葉を長くしたようだ。
オヤマボクチ参照。
2016年03月03日
アサマヒゴタイ
アサマヒゴタイ (キク科)
2010年9月10日、戸隠山。
クロトウヒレンの親戚だろうと推測して調べたら、まずセンダイトウヒレンに当たった。でも分布域が違う。アサマヒゴタイのようだ。
この2種はともに学名Saussurea nipponicaで変種程度の差のようだ。いちいち別種にするなと申し上げたい。
下の写真は葉と茎。茎に翼があるのが特徴。
2016年02月18日
ノハラアザミ
ノハラアザミ (キク科)
2010年9月10日、長野県信濃町ソバ畑脇。
頭花は垂れない、総苞にはクモ毛があるが総苞片はモリアザミより短い。
葉もモリアザミのように刺刺しくない。たぶんノハラアザミ。
モリアザミ参照。
2016年01月13日
2015年12月30日
オタカラコウ
2014年08月08日
キオン
2013年10月07日
2012年03月01日
タカネヤハズハハコ
2012年01月03日
ハンゴンソウ

ハンゴンソウ(キク科)
2010年8月5日、長野県上高地横尾付近。
草丈は高い。小さな黄色い頭花が集合して結構目立つ。
葉は羽状複葉。
同じキオン属のキオンと似るが、キオンの葉は長楕円形とのこと。
2011年12月20日
2011年12月17日
2011年12月02日
メタカラコウ
メタカラコウ(キク科)
2010年8月5日、長野県、上高地。
舌状花は1~3枚、葉はハート型で先が尖る。
オタカラコウは舌状花が5~9枚、葉の先端は尖らない。だそうです。
2011年11月26日
2011年11月24日
カニコウモリ
カニコウモリ(キク科)
2010年8月5日、長野県、上高地。
2011年11月19日
2011年08月04日
2011年06月08日
2010年12月10日
ミヤコワスレ
ミヤコワスレ(キク科)
2010年5月29日、新潟市郊外(カーブドッチの庭)。
鮮やかな青のキクが咲いていた。たぶん、ミヤコワスレ。
ミヤコワスレは野生種ミヤマヨメナから作られた園芸種とのこと。
新潟では、春に咲く野生の野ギクはミヤマヨメナしか知らない。ミヤコワスレも原種の性質を保っているようだ。
ミヤマヨメナ参照。
2010年09月15日
2010年09月09日
ミヤマアキノキリンソウ
ミヤマアキノキリンソウ(キク科)
2009年9月14日、飯豊連峰、北俣岳。
アキノキリンソウの高山型。
草丈が低い、頭花が少ないが大きい、といった点が異なる。
でもよく分からない場合もある。
高山植物。
2010年09月02日
イワインチン
イワインチン(キク科)
2009年9月14日、飯豊連峰、北俣岳。
梅花皮山荘(北俣岳避難小屋)のある鞍部で咲いていた。
葉は深裂してコスモス状だが、草丈は20cm程度しかない。
高山植物。
山行記録は飯豊連峰縦走登山、北股岳~御西岳~飯豊本山。
2010年08月10日
2010年07月23日
オクモミジハグマ
オクモミジハグマ(キク科)
ハグマ(白熊)はヤクの尾の毛で作った払子のこと。槍や兜等の飾りに使うらしい。
花がこのハグマに似ているのが名前の謂れ。
西日本に分布するモミジハグマが母種で、オクは奥州のことだろう。
オクモミジハグマ参照。
2010年07月15日
ノブキ
ノブキ(キク科)
林の中の日の当たらない所でよく咲いている。
葉が若干フキに似るのが名前の由来らしい。
頭花は、周辺部が雌花、中心部が両性花とのこと。